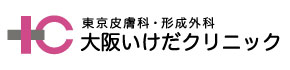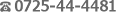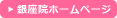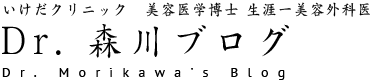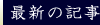正面輪郭は、黄金比率に支配されています。
レオナルドダビンチが提唱したあれです。長方形の縦横の比率として最も美しいというか、安定感がある比率。5対8をいいます。よくあるのは煙草の箱、コピー用紙なんかも近似値です。いろんなものが近い比率です。
顔の正面輪郭を長方形で囲んだら、黄金比率になるのが美しいとされています。つまりやや面長、でも長すぎない。その中に収まる顔がバランスがいいというものです。
さて、顔が長い短いは、身体の大きさつまり身長との比率ですよね。顔の上下長には頭も含むので、人種による差が少なく(頭が小さければ知能が低いということになる。)、身長との比率が、顔の相対的上下長として見られますよね。日本人をはじめとしたモンゴロイド系人種では、平均身長が男性で170cm未満
▼続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 美容医療
顔の輪郭を分析します。—先ずは側面輪郭から—
顔を横から見て下さいと言っても、自分の顔は正面からしか見る事ができないものです。合わせ鏡や三面鏡で普段から自分の顔を見る人は昨今では希少種人です。でも人間は動物の中でも3次元視ができる能力が秀でているのです。何故なら二つの目が前を向いてから、同時に二つの目で見る事ができるからです。その結果、3次元的に距離を感じる事ができるのです、凹凸を正面から見ても前後位置を感じる事ができる様に、人間では目も脳もうまく出来ています。
ところで顔を横から見て、どこが前に出ているかは、人間らしさを表出します。何故かというと、人間は特殊な動物で、顔の向き、顔の部品の使い方が他の動物と違うからです。
人間は直立する唯一の動物です。そのため、首は上に伸び、その上に頭と顔が乗っています。そのため顔は身体と同
▼続きを読む
▼続きを読む
上口唇短縮術とは?。-症例1-
口唇とは赤い唇だけでなく、医学的には鼻の下の皮膚も口唇とです。赤い唇を赤唇、肌色の唇を白唇と言い分けます。ですから、上口唇短縮術はどこかを切除縫合することになります。昔20年ほど前までは、父は赤唇縁とその上の皮膚を切除する手術をしていました。私が引き継いだ患者さんのうち何人かも受けています。口紅をしていればよく判らないのですが、よく見ると赤唇縁の微妙なカーブが消失しているため何か不自然です。
そこで、最近学会でも報告されているのですが、鼻翼基部から鼻柱基部の外鼻孔底の堤状の高まりの下に傷を持って来れば、折れかえり線なので傷跡が見えにくくなると考えられ、そこで切除するようになりました。但し、形成外科認定医が、形成外科的縫合で丁寧に縫い合わせないと、何しろ動くところですから傷跡の幅が出てき
▼続きを読む
▼続きを読む
美しい女(ヒト)の楽しみ-ミニリフトから-
私が10年以上治療させてもらってきた患者さんですが、このたび上口唇短縮術とミニリフトを施行しました。
ところで、口唇とは赤い唇だけでなく、医学的には鼻の下の皮膚も口唇とです。赤い唇を赤唇、肌色の唇を白唇と言い分けます。ですから、上口唇短縮術はどこかを切除縫合することになります。昔20年ほど前までは、父は赤唇縁とその上の皮膚を切除する手術をしていました。私が引き継いだ患者さんのうち何人かも受けています。口紅をしていればよく判らないのですが、よく見ると赤唇縁の微妙なカーブが消失しているため何か不自然です。
そこで、最近学会でも報告されているのですが、鼻翼基部から鼻柱基部の外鼻孔底の堤状の高まりの下に傷を持って来れば、折れかえり線なので傷跡が見えにくくなると考えられ、そこで切除するよう
▼続きを読む
▼続きを読む
美しい女(ヒト)の楽しみ
いよいよ、私が長年携わってきた症例写真の御紹介をいたします。
14年前の写真が見つかったそうで、送っていただけました。
昔の写真なので、画質が高くないので、トリミングはできません。患者さんも言うのですが、メイクが派手で雰囲気がよく解りません。
さらに、昔の写真と現在のセピアカラーの写真を比較します。
ところで、12月26日に鼻下短縮手術をしました。症例提示(展示と言える程の濃厚な内容。)をさせて頂く機会を得ました。今回特別に、アドバイザリースタッフとしてお願いして、症例写真の選定と経過説明と、所見について聴取させて頂き、ブログの記載時に協力いただく事になりました。願ってもない事です。
上記の2枚の写真の間に、どのような、治療をしてきたのでしょうか?。一つずつ解き
▼続きを読む
▼続きを読む