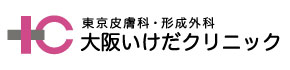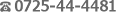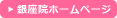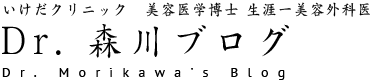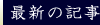美容医療の中で、皮膚科的分野は置いといて、今回は形成外科、美容外科の分野での、侵襲を伴う治療について、その機序、生理、解剖について述べたいと思います。
まず、今回は切開手術に於ける、形成外科的縫合の意味、特徴、違いについて述べると共に、形成外科の優位性についても触れます。
縫合:これまで、26年間形成外科医として、診療してきて、もっとも啓蒙が不足で、そのためもっとも残念な点。何のために、形成外科を受診するのか?。なぜ形成外科医が顔面を手術するべきなのか?。何が言いたいのかというと、私達形成外科医認定医が手術したら、傷跡が消えるに等しいからです。本当?。また偉そうなこと言ってエ~。という声が聞こえそうですし、「だって顔出し,怖いし、傷跡が残るんでしょう?。」といわれると、「じゃあ!
▼続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 美容外科
美容医療の神髄本編 ―美容医療の基本―
今を大事に生き、過去からの経験を掘り起こし、未来に向かって何をしていくべきか?。いつの世でも私達の命題ですが、医療に於いても、現在過去未来のプランが欠かせません。だから、診察が結果を決めるのです。診察は,触ったり,検査したりだけでなく、過去の経過から、求める未来像を引き出す。つまり情報が結果を導くのです。通常,医療に於いては診察前の事前情報を求めます。予診カルテと言ったり,アンケートと称したりします。姓名はもちろん,年齢、性別、住所、職業、家族構成、等が医療に必要な情報なのです。例えば、治療が危急の疾病でない場合、医療者のスケジュールと患者さんの都合の合一がなければ、成り立ちません。仕事の都合,家族の都合,通院の距離と時間等が影響します。職業については,特殊な物質に暴露する人は医学的に診療に
▼続きを読む
▼続きを読む
まぶたの機能と美容医療Ⅹ 重瞼術
これまで、まぶたの機能と美容について多方向の視点から、述べてきました。今回集大成として、重瞼術等に対する、私なりの正しいと考える点を述べたいと思います。
私の医学博士研究のテーマは「二重瞼と一重瞼の構造差」です。内容をもう一度説明します。目を開ける上眼瞼挙筋は、挙筋腱膜とミューラー筋に分かれて瞼の縁の瞼板に付いています。つまり挙筋は、まぶたの縁を挙げる構造になっています。挙筋腱膜の途中から前方に向かってコラーゲン線維の束が枝分かれしていて、皮膚またはそのすぐ深層の眼輪筋(目を閉じる筋)に付着していて、開瞼力が皮膚にも働いて、皮膚が持ち上げるような構造になっているのが、二重瞼。この構造が欠損していて、開瞼しても皮膚が置き去りになってしまうのが一重瞼。これが、本態です。この構造の差異を電子
▼続きを読む
▼続きを読む
まぶたの機能と美容医療Ⅸ 眼頭切開2 -蒙古襞(もうこひだ)について治療法-
はじめに、私達の行う目頭切開術(内眼角形成術)は、特筆すべき経過および結果をもたらします。これは形成外科の経験、解剖および生理的知識に基づいて、美容外科手術の中でも、もっとも難しい目頭切開に上手に利用する事を目的としたからです。
何度も言いますが、私達は日本で69人しかいない形成外科専門医で美容外科専門医です。実はその中には、自称ナンチャッテ形成外科医が結構います。形成外科医の中には美学の無い、古い自称美容外科医が多いのです。美容と機能を満たす見解を持つと考えられるのは、60人のうち、私達東京皮膚科形成外科、リッツ、ベリテくらいで、一部の医師がシロモトの関東や高須にいるくらいです。
前置きはさておき、手術法は多岐に渉るので簡便に説明していきます。その前に復習!。蒙古襞は、目頭部位
▼続きを読む
▼続きを読む
まぶたの機能と美容医療Ⅷ 眼頭切開 -蒙古襞(もうこひだ)について-
モーコひだって何?。まぶたの機能と美容Ⅰで記しました。一重まぶたに付随する構造です。といっても覚えていないでしょう。ではもう一度。ところで、【まぶたの機能と美容】のテーマですが、機能には関係ないんじゃなねぇ⤴?と、思われるかもしれませんが、大ありなんです。これから説明します。
一重瞼の遺伝子は、約2万円前に北方アジアでの突然変異の結果生じて、現在まで北東アジアではその遺伝子の存在が継続していることは、今まで述べてきました。北東アジアってどこ?、今でいうモンゴルです。中国の北漢字を漢字で蒙古と書きます。そして日本人は、南アジア出身の、古いアジア(モンゴロイド)系と、北東アジア出身の新アジア(モンゴロイド)系が混血していると考えられています。遺伝子も混合しています。ところで、蒙古斑というの
▼続きを読む
▼続きを読む