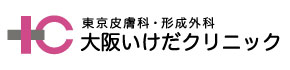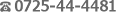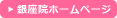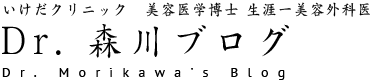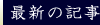なんかまた、振りかぶって書き始めましたが、本日のニュースに触発されてしまったのです。とは言っても別に、世界の美容医療の番組を見た訳ではありません。現今の国際情勢に於ける、美容医療に対する態度が様々である事を、感じていたので、述べてみようと思っただけです。
美容医療の分野、日本では美容外科と形成外科があり、その理由は歴史のブログで触れました。実は日本だけの様です。漢字使用国でも、中国では成形外科が、韓国でも整形外科が美容医療を、担っています。逆に欧米では、Plastic Surgeryは形成外科を意味し、Aesthetic Sugeryは美容外科を意味します。米国ではPlasic and reconstrucive surgery形成再建外科とか、Aesthetic Plastic su
▼続きを読む
美容医療は文化です。文明です。—正義の戦争と、退廃した平和のどちらを選びましょうか?。
時事問題は語らないつもりでしたが、私達美容医療に携わる者と国民を、時代が違う方向にいざなう可能性を感じるので、普遍的な論議を述べ、美容医療のあるべき姿を語りたいと思います。
文明とは、技術です。科学技術、経済学、政治技術、法律。民主主義国家なら、これらを持って国民を経済的に豊かにする。言ってみれば、楽に生きられる様にする事です。国民一人一人が技術を磨き発揮する事で、すべての国民が互いに豊かさを享受でき、こうして国民国家が興隆する筈だという方策です。
文化は、どうやって生きる為ではなく、何の為に生きるかを考える事です。脳の前頭葉の働きです。例えば食事を生きる為だけに食べる。腹が減ったから食べる。またはその為に働くのは、文明です。それに対して、どんな食事を楽しむかは、食文化ですよね。
▼続きを読む
▼続きを読む
続きで、話が飛んで、視力について-眼瞼下垂と関係があるような?ないような?‐Ⅲ
視機能の編の、続きの続きで網膜です。像を結んで光を感知し、神経に信号を与える臓器、カメラではフィルムです。網膜は視信号を作るところなので、信号を送る神経や信号を受けて脳内に像を造る脳の話も加わります。
その前に前回書き忘れた白内障の件を書き足します。
白内障は、水晶体の透過性低下です。加齢によることが多く、だれでも必ず年齢とともに生じます。薬剤性や、先天性や、物理的な要因もあり得ますが、ほとんどは加齢性です。視力としては、すりガラスを通してみていることになる訳で、ぼやけるのです。老視も同時に進むので、近くが見にくくなり、離すとぼやけるので、字が読みにくくなります。手術で人工レンズに入れ替えれば治せるのですが、屈折調節ができなくなります。レンズをどの焦点に設定するかですが、日常生活
▼続きを読む
▼続きを読む
続きで、話が飛んで、視力について-眼瞼下垂と関係があるような?ないような?‐Ⅱ
続きです。
水晶体は、ご存知の通りレンズですよね。とは言っても、カメラのレンズはガラスですから、厚さを変えられないので、前後に位置を変えてピントを合わせます。しかし、人間のレンズはガラスではなく、軟らかく厚さが変えられる仕組みです。厚みを変えられるということは、屈折率をかえることができると言う事です。凄いですよね。ここで屈折が出てきました。目に入ってきた光は、水晶体で曲がって、近くの物を見る時は水晶体が厚くなって(丁度遠視や老視の人が厚いレンズの眼鏡をかけているのと同じですね。)網膜に像を結びます。遠くを見る時は、水晶体が扁平になってピントを合わせます。これが屈折です。
よくカメラや目の仕組みを説明する絵として見ますよね。ろうそくが網膜で逆さに映ったり、フィルムに写るヤツ。レンズ
▼続きを読む
▼続きを読む
続きで、話が飛んで、視力について-眼瞼下垂と関係があるような?ないような?‐Ⅰ
眼球が視機能の主体なのですが、本来は眼科医が担当する臓器です。ところが、眼科医は、検査するばかりで説明が下手な様です。私の患者さんと話していても、的を得ない説明しか受けていない場合が多いです。
それはそれとして、眼球は前から、角膜、前房、虹彩、水晶体、硝子体、そして網膜があります。そのどれもが視機能に関与します。つまり、光がちゃんと通るか、通った光が網膜にちゃんと像を投影するかです。よくカメラに凝らせられますので、引用します。写真は私達形成美容外科医に取っては、欠かせない物です。ちなみに私は、中学生時にアサヒペンタックス(今は無い名器です。)を買ってもらい、のめり込みました。カメラを勉強しました。また星空に夢を見て、天体望遠鏡も買ってもらいました。だから、レンズや画像投影には科学的な知
▼続きを読む
▼続きを読む